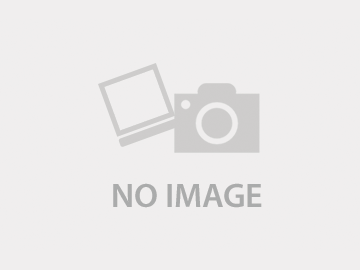化学肥料は二十世紀の後半になって ますます重要になってきた
たとえば、「化学肥料をまけば、土がカチカチの固まりになってしまい、ミミズが死に土も死ぬ」、「化学肥料で育てた稲の種籾(たねもみ)は発芽が悪い」、「化学肥料を使ったリンゴは堆肥で育てたリンゴより味が悪い」、「化学肥料で育てた野菜が持っているビタミンは堆肥で育てた野菜の半分もない」などである。
しかし、その後都市の肥大、化学肥料の普及、農村部の疲弊・高齢化といった変化が急激に起き、都市ごみの処理は大きな転機を迎えることとなります。
もしも、世界人口が現在の倍になってしまったら、地球は、はたして人類を養っていけるだろうか?いまでも、貧乏な人たちは充分な食事ができない。食料のたりない国では餓死者も出ているという。それが、六十億にも増えてしまったら、どうなるのだろうか。イギリスの科学者バナールによれば、人類が戦争のない世界を作り、よりすぐれた化学肥料や農業薬品を使うならば、食料の増産の問題は解決できるといっている。だが、現実はそううまくいっていないようである。むずかしい問題である。いまいえることは、理性や科学の力を信頼して、より農業を科学的にしていくこと、そのために人類が平和のことをまじめに考えあうことだと思う。そこで、これから農薬のことをとりあげてみよう。作物は化学肥料だけやればよく育つわけではない。天候も農業のためには大切な条件である。作物の敵、病虫害をふせがないでいれば、作物は目の前で全滅してしまうとさえいえる。ここ数年、日本の稲はよくそだち、毎年豊作がつづいているが、その影には、農業薬品(略して農薬という)のふんだんな使用がある。野生の植物は、動物をよせつけない苦味や毒を自分で作って、自然に自分のからだを守っている。私たちのたべる野菜やくたちのは、農薬などを使って、守ってやらなければならないのである。明治時代には、日本のリンゴは、リンゴワタムシという害虫によって、ひどいめにあった。それが、大正時代になって、硫酸ニコチンという殺虫剤が使われるようになってから、毎年おいしいリンゴがたべられるようになったのである。農薬の進歩は、食料の増産に、重大な影響をあたえるのである。私たちは、ここで、第二次世界犬戦後に突然あらわれ、そして急速に全世界に広まったDDTという農薬のひとつが、どのようにつくられたかを考えてみよう。
農水省は、農業の環境負荷低減を目指す「みどりの食料システム戦略」で、モデル地域の創出に向けた「推進交付金」を活用する地域が、約300件に上る見込みだと明らかにした。化学肥料・農薬や温室効果ガスの削減...
明治時代に、日本でも化学肥料の生産と肥効試験などの研究が開始された。明治20(1887)年、タカジアスターゼの発明で有名な高峰譲吉が、実業家の渋沢栄一から支援を得て「東京人造肥料会社」を設立した。高峰は、自らが社長兼技師長となって、日本最初の化学肥料製造の指揮を執ることになる。この会社は、現在の江東区大島1丁目にあった。都立科学技術高校の横に小さな釜屋堀公園があり、その一角には「化学肥料創業記念碑」と「尊農」の碑が建てられている(写真1)。
第二次世界大戦後、農地改革を契機とする農村の大きな変化と化学肥料の普及により、農村がし尿を肥料として利用しなくなると、行き場を失ったし尿の処理が問題になってきました。我が国の経済も戦後の復興期に入り、都市化の進展に伴って、ごみの処分も大きな問題になってきました。この当時、ごみ、し尿は海洋投棄や土地投棄処分に頼っており、ごみの処分場はカ、ハエの発生がひどく、不衛生なものが多い状態でした(図4-2-5)。
一方でリービッヒは、厩肥は土壌中から微量のミネラルを供給することが主な役割であると考え、植物へ窒素を供給するには大気中のアンモニアや土壌中の硝酸塩の方が重要だと考えていました。リービッヒはミネラルを効率的に供給すると植物の生育はよくなると考え、1845年から「化学肥料」の開発に着手しました。
一方、明治26(1893)年に、農商務省農事試験場(本場および6支場)が設立され、化学肥料の肥効試験が始まる。明治28(1895)年から5カ年間にわたって、全国各地の農耕地土壌について肥料三要素(窒素、リン酸、カリ)試験が実施され、科学的なデータの収集が行われた。その後も土壌肥料に関する試験研究は脈々と続けられ、わが国の食料増産に向けて大きな実績を残したのである。
この化学肥料製造工場は、大正12(1923)年の関東大震災で倒壊したため、操業を中止することになるが、日本における化学肥料製造の先駆けとして果たした役割は大きい。
朝日新聞の小説欄に、有吉佐和子の『複合汚染』が連載されたのは今から30年以上前の1974年である。その後この小説は、単行本や文庫本としても出版され、日本の社会と農業に大きな影響を与えた。この本には、農薬とともに化学肥料への批判が随所に出てくる。しかし、それらの化学肥料批判は、そのほとんどが著者の思い込みであり科学的根拠に乏しいものである。
化学肥料と有機質肥料には、それぞれ長所と短所がある。化学肥料の長所は、少しの量で大きな増収効果が期待できることである。有機質肥料の長所は、肥料としての効果以外に、土壌を軟らかくしたり緩衝機能を高めたりすることにある。しかし、いずれの肥料も過剰に施用すれば、問題を引き起こす。化学肥料では、土壌の酸性化や環境汚染の問題が生ずる。一方、有機質肥料のみで農産物の高い収量を得ようとすれば、かなりな多量施用が必要となり、これまた環境汚染につながってしまう。
鉱物質というのは塩化カリ・過りん酸石灰・硫安のような無機化合物なのである。化学肥料は二十世紀の後半になって、ますます重要になってきた。化学肥料を作る工業は、化学工業の代表といわれるくらいである。リービッヒがもしもいま生きかえって、現代の化学肥料工場を見るならば、きっと感心するにちがいない。五章 空気から窒素肥料を作る 《窒素肥料》 topドイツと日本の硫安工業の始りまえの話からわかるようにリービッヒの化学肥料というのは、カリとりん、つまりおもに塩化カリ(岩塩)と過りん酸石灰のことであった。ところが、窒素肥料、たとえば硫酸アンモニウム(硫安)とか、硝酸ナトリウム(チリ硝石)とかも、大切な化学肥料である。すでにリービッヒの生きていたころ、イギリスでは、石炭の蒸し焼き(乾留)のさいにできるアンモニア水と、硫酸を反応させてつくった硫酸アンモニウムが、どんどん窒素肥料として使われていた。しかし、石炭の蒸焼きからできるアンモニア水から、硫安を作るには、原料に限度があった。そのためヨーロッパの畑には、窒素肥料が不足していく一方だった。そこで硫安のほかに、天然にある窒素肥料がさがしもとめられた。その結果、チリ硝石(硝酸ナトリウム)がすぐれていることがわかり、十九世紀のすえには、ヨーロッパの畑には、大量のチリ硝石が使われるようになった。1 世界的飢餓をふせごう!だが、チリ硝石にだってかぎりがある。クルックス放電管で有名なイギリス科学者ウィリアム・クルックス卿は、一八九八年(明治三十一年)に次のような警告を行った。「諸君! いまや、全世界の小麦の収穫は、チリ硝石にかよりかっているのである。もしも空気中の窒素を、人工的に化学肥料の形にできないなら、世界的な大飢餓はさけられないことになるだろう。」このクルックス卿の発言は、イギリスよりもドイツに大ショックであった。なぜかというと、当時イギリスは海外にゆたかな植民地をもっていて、食物にはこまらなかった。ところが、ドイツは植民地はなく、チリ硝石のでる土地はもっていなかったし、土地の力はだんだん衰えるばかりであった。ドイツの科学者も、この空気中にいくらでもある窒素ガスに、目をつけたことはいうまでもない。なんとか窒素をつかまえて、これを肥料のようなものにできないものか?つまり、空中窒素の固定法ということが、まじめに考えられるようになった。ドイツ以外の国々でも、「空中窒素の固定法を研究せよ!」という気運がもりあがってきた。
かと言って、日本では現在のレベルの使用量でなければ作柄が維持できないかと言うと、そうとは言えない。化学肥料、農薬とも、現在の使用量よりも少なくすることは可能だ。筆者自身の栽培指導の中心は、この方向の推進だ。化学肥料や農薬が大量に使用されれば、生産コストを高めるだけではなく、環境への負荷も高まる可能性が大きい。だから日本でも、それらの使用量を減らすべきだ。
昭和30年代に入ると、経済成長と共に化学肥料の生産が増加し、全国に普及するにつれて、肥料として活用されていたし尿は、農村での役割を失っていき、各都市では、ごみ、し尿の処理技術の開発に苦慮していました。急激な経済成長の中で、ごみの量、質の双方が大きく変化し、経済成長のひずみを背負った各自治体のごみ処理行政の苦難の時代であったと言えましょう。
この『複合汚染』以後、国民の一部はその呪縛(じゅばく)(マインド・コントロール)にかかってしまい、化学肥料を敵視して有機質肥料のみを尊重するようになる。最近になって、土壌肥料学の立場から、かつての『複合汚染』の論調に異議を唱える論文が多数出てきた。また日本土壌肥料学会は『肥料をかしこく使おう!』という小冊子を作って、一般市民への化学肥料の説明に努力している。思い込みや誤解を解くには、長い時間と大変なエネルギーが要るようである。