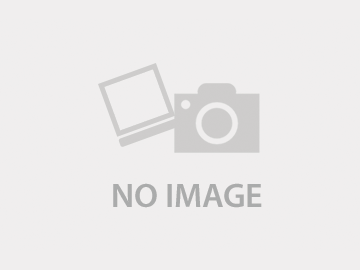これが化学肥料が周囲の自然環境へ及ぼす悪影響だ
他方、農業研究の将来方向を見渡せば、「新しい知見や知恵というものは、世界で驚異的に増えるデジタルデータの山に埋もれていて、適切に探し出すソフトウエアと十分な人材があれば、10年以内に我々の研究の80%は、データセットの分析に依存することになろう(ビッグデータの賢い活用;Getting wise to big data ; Wageningen World 2016年第2号)」のような考え方が非現実的とは思えないほど、昨今のデジタルデータの蓄積には目覚ましいものがある。
そして、化学肥料の発明が食料増産に果たした役割はきわめて大きいのである。世界最初の化学肥料の生産は、イギリスで1840年代に、過リン酸石灰の製造が試みられたころにあるとされている。世紀が変わって1909年には、ドイツの化学者F・ハーバーが空気中に無尽蔵に存在する窒素ガスからアンモニアを合成する実験に成功する。この功績により、ハーバーは1918年にノーベル化学賞を受賞している。その後、ハーバー法の改良に挑戦したK・ボッシュは、高圧化学の技術を用いてアンモニアの大量生産に成功する。この功績により、ボッシュもまた1931年に、技術者としては最初のノーベル化学賞を受賞している。この二人の科学者の名前に因(ちな)んで、空中窒素から窒素肥料を作る技術を「ハーバー・ボッシュ法」と呼ぶのである。
明治時代に、日本でも化学肥料の生産と肥効試験などの研究が開始された。明治20(1887)年、タカジアスターゼの発明で有名な高峰譲吉が、実業家の渋沢栄一から支援を得て「東京人造肥料会社」を設立した。高峰は、自らが社長兼技師長となって、日本最初の化学肥料製造の指揮を執ることになる。この会社は、現在の江東区大島1丁目にあった。都立科学技術高校の横に小さな釜屋堀公園があり、その一角には「化学肥料創業記念碑」と「尊農」の碑が建てられている(写真1)。
化学肥料と有機質肥料には、それぞれ長所と短所がある。化学肥料の長所は、少しの量で大きな増収効果が期待できることである。有機質肥料の長所は、肥料としての効果以外に、土壌を軟らかくしたり緩衝機能を高めたりすることにある。しかし、いずれの肥料も過剰に施用すれば、問題を引き起こす。化学肥料では、土壌の酸性化や環境汚染の問題が生ずる。一方、有機質肥料のみで農産物の高い収量を得ようとすれば、かなりな多量施用が必要となり、これまた環境汚染につながってしまう。
また尊農の碑には、化学肥料工場を設立した背景と意義が格調高い漢文調の文章で刻まれている。この大要を、現代文に直すと次のようになる。
なぜ、有機肥料は捨てられてしまうのか?化学肥料の代替にならないのだろうか?次回、慣行農法と有機農法、環境保全型農業、環境再生型農業(リジェネラティブ農業)の違いについて詳しく述べる事で、有機肥料への移行の課題について迫りたい。
朝日新聞の小説欄に、有吉佐和子の『複合汚染』が連載されたのは今から30年以上前の1974年である。その後この小説は、単行本や文庫本としても出版され、日本の社会と農業に大きな影響を与えた。この本には、農薬とともに化学肥料への批判が随所に出てくる。しかし、それらの化学肥料批判は、そのほとんどが著者の思い込みであり科学的根拠に乏しいものである。
外部から作物が必要とする以上の栄養を与えれば、過剰な分は自然界に流れ出る。流れ出た栄養が環境や人体へ悪影響を及ぼす。これが化学肥料が周囲の自然環境へ及ぼす悪影響だ。
驚異的なリサイクル率を誇る韓国でさえも、リサイクルされた堆肥や飼料は売れ残り、捨てられてしまう現実がある。
化学肥料生産には別の圧力もかかっている。地球温暖化対策として中国はじめ肥料輸出国が生産を抑制、国内需要を優先し、輸出を制限し始めていることだ。中国政府は2021年11月に化学肥料の輸出制限を開始した。もともと原料のリン鉱石の枯渇が現実化しつつあり、リンも先行き、さらに需給がひっ迫しかねない。
たとえば、「化学肥料をまけば、土がカチカチの固まりになってしまい、ミミズが死に土も死ぬ」、「化学肥料で育てた稲の種籾(たねもみ)は発芽が悪い」、「化学肥料を使ったリンゴは堆肥で育てたリンゴより味が悪い」、「化学肥料で育てた野菜が持っているビタミンは堆肥で育てた野菜の半分もない」などである。
だからこそ、今よりも窒素の利用効率が高い栽培技術や、作物や家畜の食用にならなかった残渣の肥料としての循環利用などが、ますます大切になる。その際に、そうした循環利用を重視している有機農業は当然重要だが、有機農業だけで、世界人口を養う食料が確保できるはずがない。今でも世界人口の約半分が窒素肥料によって育った食料を食べているのだから、化学肥料をなくしたら、世界は大飢饉に襲われてしまう。食料増産と環境保全の両立を図る一層の技術開発と、そのための社会政策が必要となっている。
「緑の革命」は、アジアでのコメ、中央アメリカ・アジアの一部地域でのコムギの増産に大いに貢献したが、アフリカでは幾つかの理由により、十分な成果は得られていない。栄養摂取も大きくは改善されず、発育阻害の発生率は高止まりし、その絶対数はむしろ増えているという。このことは、政府支援や世帯収入の増加、教育の改善など食料増産以外の取組が必要と説明している。
素人考えでは、化学肥料に課題があるならば、有機肥料を使えば良いではないか!と思いたくなる。
その後さらに、化学肥料の製造技術は多くの研究者によって改良され、より品質のすぐれた安価な肥料が生産されるようになる。そして、これらの化学肥料の利用により、ヨーロッパやアメリカ大陸の農作物の生産量は急速に伸びてゆくのである。20世紀の増加する人口をカバーするに足りる食料の生産量を確保することができた。